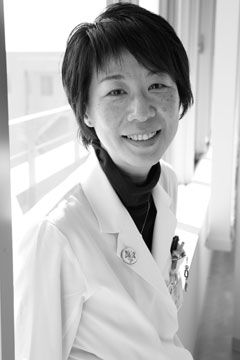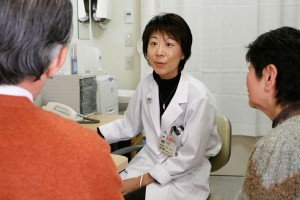アメリカでの経験を日本の医療に役立てたい
「緩和ケア」というと、まだまだ終末期医療をイメージされる方が多いように思います。しかし、必ずしもそうではありません。「診断が信じられない」「毎晩不安で眠れない」という初期の段階から、闘病中に再発や転移がわかったとき、そして穏やかな最期へと向かう終末期まで、病期の幅広い段階が緩和ケアの対象です。
静岡がんセンターでは、「この病院には、気持ちや考えの整理をサポートする専門スタッフがいるんですよ。一度話をしてみてはいかがですか」と、医師や看護師が、患者さんに緩和ケアを勧めています。また、患者さんやご家族が直接相談できる「よろず相談」という窓口があって、そこから私たちにサポート依頼が来ることもあります。
ときどき「カウンセリングに頼らなきゃいけないのは、私の心が弱いからだ」という方がいらっしゃいます。しかし、そうではないんです。私たちと話をするうちに、弱音を吐くことと心が弱いのとは違うということに気付かれたり、自分の気持ちと向き合ったり、つらさと折り合いをつける工夫を見出すなかで、自分のたくましさを知り、闘病の力をつけられるという方は、たくさんいらっしゃいます。
私はアメリカの大学院で勉強して、「臨床ソーシャルワーカー」の資格をとりました。ニューヨークにある終末期がん専門病院のカルヴァリー・ホスピタルに勤務していたとき、研修に来られた田中桂子先生に出会ったことが、現在の職場で仕事をするきっかけです。田中先生から、静岡がんセンターの緩和医療科と緩和ケア病棟の立ち上げに向けた構想を伺ったんですね。それまでも日本で仕事がしたくて、ずっと探していました。しかし、なかなか希望にあうところが見つからなくて、気がつけば10年間以上、ニューヨークに暮らしていました。2001年の「9.11」以降は、正直、「志半ばで帰国できなかったら」と思うこともありました。
2002年7月から静岡がんセンターに勤務し、緩和医療体制の立ち上げを、ゼロから関わらせていただきました。それまでの経験が活かすことができたのは幸運でしたね。開院初日から、依頼をいただいたのも嬉しかった。
日本でも、がん医療や緩和ケアの領域で仕事をしている心理療法士や臨床心理士は、年々増えています。現在、全国で200~300人ぐらいかと思います。
静岡がんセンターでは、「この病院には、気持ちや考えの整理をサポートする専門スタッフがいるんですよ。一度話をしてみてはいかがですか」と、医師や看護師が、患者さんに緩和ケアを勧めています。また、患者さんやご家族が直接相談できる「よろず相談」という窓口があって、そこから私たちにサポート依頼が来ることもあります。
ときどき「カウンセリングに頼らなきゃいけないのは、私の心が弱いからだ」という方がいらっしゃいます。しかし、そうではないんです。私たちと話をするうちに、弱音を吐くことと心が弱いのとは違うということに気付かれたり、自分の気持ちと向き合ったり、つらさと折り合いをつける工夫を見出すなかで、自分のたくましさを知り、闘病の力をつけられるという方は、たくさんいらっしゃいます。
私はアメリカの大学院で勉強して、「臨床ソーシャルワーカー」の資格をとりました。ニューヨークにある終末期がん専門病院のカルヴァリー・ホスピタルに勤務していたとき、研修に来られた田中桂子先生に出会ったことが、現在の職場で仕事をするきっかけです。田中先生から、静岡がんセンターの緩和医療科と緩和ケア病棟の立ち上げに向けた構想を伺ったんですね。それまでも日本で仕事がしたくて、ずっと探していました。しかし、なかなか希望にあうところが見つからなくて、気がつけば10年間以上、ニューヨークに暮らしていました。2001年の「9.11」以降は、正直、「志半ばで帰国できなかったら」と思うこともありました。
2002年7月から静岡がんセンターに勤務し、緩和医療体制の立ち上げを、ゼロから関わらせていただきました。それまでの経験が活かすことができたのは幸運でしたね。開院初日から、依頼をいただいたのも嬉しかった。
日本でも、がん医療や緩和ケアの領域で仕事をしている心理療法士や臨床心理士は、年々増えています。現在、全国で200~300人ぐらいかと思います。
父への告知を悩んだことが最初のきっかけ
私は両親をがんで亡くしています。母は、私が日本の大学を卒業した87年、乳がんで亡くなりました。父は90年12月に胃がんだとわかり、入院からわずか3カ月で逝ってしまった。母のときは長期の療養を経て亡くなったので、少しずつ心の準備をすることもできましたが、父のときは最初から状況が切迫していました。「緊急入院した」という知らせを受けたとき、私はニューヨーク大学大学院の学生でした。12月24日のクリスマスイヴの日で、取るものもとりあえず帰国したんです。
当時は「がんは告知するべきか」ということが、社会的にも盛んに議論されていて、私は「ちゃんと話をしたほうがいい」と思いました。しかし、父の弟にあたる叔父に「そんなことをして責任をとれるのか」と言われまして、モヤモヤしたものを感じながらも、何としてでも告知するというところまでは、踏み切れずにいたんです。
父は診断がついた時点で、開腹手術も化学療法もできないことがわかりました。状態が日に日に悪化していくなかで、「自分は何もしてあげられない」という不甲斐なさを感じていました。今にして思えば、父はがんだということを、わかっていたんじゃないかと思います。でも、帰国した私に元気な素振りを見せる父に対し、私も何事もないかのように振る舞ってみたり、お互い演技しているような状況に、「これでいいのか」という疑問を感じながらも、どうしていいかわからなかった。
当時は「がんは告知するべきか」ということが、社会的にも盛んに議論されていて、私は「ちゃんと話をしたほうがいい」と思いました。しかし、父の弟にあたる叔父に「そんなことをして責任をとれるのか」と言われまして、モヤモヤしたものを感じながらも、何としてでも告知するというところまでは、踏み切れずにいたんです。
父は診断がついた時点で、開腹手術も化学療法もできないことがわかりました。状態が日に日に悪化していくなかで、「自分は何もしてあげられない」という不甲斐なさを感じていました。今にして思えば、父はがんだということを、わかっていたんじゃないかと思います。でも、帰国した私に元気な素振りを見せる父に対し、私も何事もないかのように振る舞ってみたり、お互い演技しているような状況に、「これでいいのか」という疑問を感じながらも、どうしていいかわからなかった。
季羽先生のアドバイスのおかげで視野が開けた
そんなとき、救いの手を差し伸べてくださったのが、季羽倭文子(きばしずこ)先生でした。季羽先生は、日本のホスピスケアの黎明期を支えた第一人者のおひとりです。季羽先生の連絡先を教えて下さったのは、現在、国立がん研究センター緩和治療科に勤務されている的場元弘先生。的場先生は当時、ニューヨークに留学されていて、本当に偶然のつながりなのですが、ホームパーティーにお邪魔したことがあったんです。
的場先生の書斎に、終末期医療関連の本がたくさんあるのを見て、「貸して下さい」とお願いしました。私はその頃、社会学を勉強していましたが、母のことがあったので、気になる分野ではありました。父が緊急入院したのは、その2ヶ月後のことです。的場先生に連絡したら「困ったことがあったら、この人に連絡してごらん」と、季羽先生をご紹介くださった。
季羽先生は、父が入院している病院まで来てくださりました。叔父と弟と私の3人と話をするなかで、「病名を伝える伝えないは、そんなに大事なことではありませんよ」と言われました。「ご自分の命がそれほど長くないことは、すでに気付いらっしゃるかもしれません。今できることとして、少しでも身体が楽になるようなケアをしてあげてはいかがですか」。そうアドバイスしてくださった。
真実を伝えないということは、ちゃんと向き合っていないことなんじゃないか――。私は、ずっとそういう後ろめたさに捕らわれていたのですが、それ以外にも選択肢があることを季羽先生に教えていただいて、気持ちがとても楽になりました。同時に、医療の素人の私たちにできることを、季羽先生がポンとテーブルに乗せてくださったおかげで、視野が広がりました。 おかげさまで、父の最期は本当に静かなものでした。その瞬間、「どうして息をするのを忘れちゃってるの?」と思ったくらい、すーっと降りていくような感じでしたね。私たちにも、「できることはしてあげることができた」という充足感がありました。
的場先生の書斎に、終末期医療関連の本がたくさんあるのを見て、「貸して下さい」とお願いしました。私はその頃、社会学を勉強していましたが、母のことがあったので、気になる分野ではありました。父が緊急入院したのは、その2ヶ月後のことです。的場先生に連絡したら「困ったことがあったら、この人に連絡してごらん」と、季羽先生をご紹介くださった。
季羽先生は、父が入院している病院まで来てくださりました。叔父と弟と私の3人と話をするなかで、「病名を伝える伝えないは、そんなに大事なことではありませんよ」と言われました。「ご自分の命がそれほど長くないことは、すでに気付いらっしゃるかもしれません。今できることとして、少しでも身体が楽になるようなケアをしてあげてはいかがですか」。そうアドバイスしてくださった。
真実を伝えないということは、ちゃんと向き合っていないことなんじゃないか――。私は、ずっとそういう後ろめたさに捕らわれていたのですが、それ以外にも選択肢があることを季羽先生に教えていただいて、気持ちがとても楽になりました。同時に、医療の素人の私たちにできることを、季羽先生がポンとテーブルに乗せてくださったおかげで、視野が広がりました。 おかげさまで、父の最期は本当に静かなものでした。その瞬間、「どうして息をするのを忘れちゃってるの?」と思ったくらい、すーっと降りていくような感じでしたね。私たちにも、「できることはしてあげることができた」という充足感がありました。
ソーシャルワーカーを目指し大学院に再入学
父が亡くなった後、「季羽先生にどうお礼をしたらいいんだろう」とい気持ちがあって、「私にできることがあったら何でも言ってください」とお願いしました。もちろん医療のことは何も知りませでしたが、大学院は1年間の休学手続きを取っていたので、時間はありました。
それで先生が当時、代表兼世話人をしておられたホスピスケア研究会などで、通訳を務めさせていただくチャンスをいただいたんです。アメリカやイギリス、デンマークなどから専門家を招き、各国のホスピスや緩和ケアの現状を伝える講演会があると、季羽先生からお呼びがかかりました。実は、その初めての仕事が、後に勤務することになるカルヴァリー・ホスピタルの看護師の招待講演でした。
ホスピスケア研究会の参加者の多くは看護師でしたが、なかには大学の先生や医師などもいました。通訳をし、研究会に参加するうちに気付いたのは、日本の病院にも、私たちが季羽先生にしていただいたように、患者や家族の相談に乗ってくれる「ソーシャルワーカー」という人たちがいること。両親の入院中は、その存在にすら気付きませんでしたが、「自分もそういう仕事がしてみたい」と思うようになりました。
資料を取り寄せ、情報を集めていくうちに、日本とアメリカの大学院とでは、病院などでの実習の有無という点で大きな違いがあることがわかりました。医療の現場で臨床の経験を積みたかったので、社会学のほうは辞めることにして、92年9月から2年間、特に実習先が充実しているコロンビア大学大学院に入り直しました。
それで先生が当時、代表兼世話人をしておられたホスピスケア研究会などで、通訳を務めさせていただくチャンスをいただいたんです。アメリカやイギリス、デンマークなどから専門家を招き、各国のホスピスや緩和ケアの現状を伝える講演会があると、季羽先生からお呼びがかかりました。実は、その初めての仕事が、後に勤務することになるカルヴァリー・ホスピタルの看護師の招待講演でした。
ホスピスケア研究会の参加者の多くは看護師でしたが、なかには大学の先生や医師などもいました。通訳をし、研究会に参加するうちに気付いたのは、日本の病院にも、私たちが季羽先生にしていただいたように、患者や家族の相談に乗ってくれる「ソーシャルワーカー」という人たちがいること。両親の入院中は、その存在にすら気付きませんでしたが、「自分もそういう仕事がしてみたい」と思うようになりました。
資料を取り寄せ、情報を集めていくうちに、日本とアメリカの大学院とでは、病院などでの実習の有無という点で大きな違いがあることがわかりました。医療の現場で臨床の経験を積みたかったので、社会学のほうは辞めることにして、92年9月から2年間、特に実習先が充実しているコロンビア大学大学院に入り直しました。
1年目の実習で確信した「これが私の進む道」
大学院1年目の実習先は、何と驚いたことに、カルヴァリー・ホスピタルでした。今思い返しても、不思議な縁を感じますね。しかし、「自分がやりたいことと、実際にできることは違う」という分別はありましたから、とにかく1年間、現場を経験してみて、自分がこの仕事に向いているかどうかを見極めようと思いました。結果から言うと、カリヴァリーでの体験は、本当に素晴らしいものでした。
私が生まれて初めて担当した患者さんは、リンという名の、AIDS関連疾患で子宮がんを患っている女性。シングルマザーで、息子さんが刑務所に入っていて、ご両親とは疎遠など、いろんな問題を抱えていましたが、とてもバイタリティがある人でした。母国語も違うし、カウンセラーとしては何も知らない「ピヨピヨ」の初心者の私に、胸のうちを話してくれるかどうか、もちろん不安はありましたが、その辺については考慮したうえで、スーパーバイザーは担当の患者さんを人選しているのでしょうね。「どうしたら息子と再会できるかしら」「私にとってキレイでいることが本当に大切なの」――リンとは最初から、そんなやりとりがありました。
病院での実習は週に3日間。患者さんとのやりとりを逐一記録して、どんなテーマで対話したか、どういうふうに対話が展開していったかを、スーパーバイザーと共に細かく分析していきます。少しずつ担当の患者さんを増やしていって、最終的には35人の患者さんを担当しました。カルヴァリーで沢山の患者さんの看取りに関わるなかで、私自身、父親の死を思い出し、振り返る時間が、喪の作業となる経験もしました。セラピストが自分の喪の作業をしっかりしていることは、この領域の仕事に携わるにあたり大切なことだと思います。
個別カウンセリングとともに、患者さんの家族や遺族を対象にしたグループカウンセリングのサポートもありました。サポートグループの進行や運営を行うファシリテーションを学びながら、同じようなつらさを抱える者どうしの「つながる力」「支え合う力」を教えてもらいましたね。
患者さんの病状が日々変わっていくなかで、どうニーズに寄り添っていけばいいか、他のチームとどう連携していくかについても、実践を通じで学びます。また、患者さんに痛みがあるとき、痛みから気をそらすための注意転換法やリラクセーション法の導入、言葉でやりとりできなくなった患者さんの思いを、表情やしぐさから読み取るコミュニケーションなども体験しました。
「やっぱりこれが私の進みたい道だった」ということは、1年目で確信することができました。
私が生まれて初めて担当した患者さんは、リンという名の、AIDS関連疾患で子宮がんを患っている女性。シングルマザーで、息子さんが刑務所に入っていて、ご両親とは疎遠など、いろんな問題を抱えていましたが、とてもバイタリティがある人でした。母国語も違うし、カウンセラーとしては何も知らない「ピヨピヨ」の初心者の私に、胸のうちを話してくれるかどうか、もちろん不安はありましたが、その辺については考慮したうえで、スーパーバイザーは担当の患者さんを人選しているのでしょうね。「どうしたら息子と再会できるかしら」「私にとってキレイでいることが本当に大切なの」――リンとは最初から、そんなやりとりがありました。
病院での実習は週に3日間。患者さんとのやりとりを逐一記録して、どんなテーマで対話したか、どういうふうに対話が展開していったかを、スーパーバイザーと共に細かく分析していきます。少しずつ担当の患者さんを増やしていって、最終的には35人の患者さんを担当しました。カルヴァリーで沢山の患者さんの看取りに関わるなかで、私自身、父親の死を思い出し、振り返る時間が、喪の作業となる経験もしました。セラピストが自分の喪の作業をしっかりしていることは、この領域の仕事に携わるにあたり大切なことだと思います。
個別カウンセリングとともに、患者さんの家族や遺族を対象にしたグループカウンセリングのサポートもありました。サポートグループの進行や運営を行うファシリテーションを学びながら、同じようなつらさを抱える者どうしの「つながる力」「支え合う力」を教えてもらいましたね。
患者さんの病状が日々変わっていくなかで、どうニーズに寄り添っていけばいいか、他のチームとどう連携していくかについても、実践を通じで学びます。また、患者さんに痛みがあるとき、痛みから気をそらすための注意転換法やリラクセーション法の導入、言葉でやりとりできなくなった患者さんの思いを、表情やしぐさから読み取るコミュニケーションなども体験しました。
「やっぱりこれが私の進みたい道だった」ということは、1年目で確信することができました。
安らかな死は残された人へのギフトになる
カルヴァリー・ホスピタルに入院してくるのは、がん終末期の患者さんですから、入院して1週間以内に亡くなる場合もあります。ただ、私が実習生だった頃は、比較的長期の患者さんもいらして、長い方だと半年間フォローできました。
非常にケアが充実している病院なので、どの患者さんも入院初日に、顔つきが和らぐんです。前にいた病院ではこんなに大変だったとか、闘病のしんどさを話して下さることもあれば、人生を振り返えられたり、それぞれの思いを大切な人たちに伝えたり……。カウンセリングを通じて、患者さんのさまざまな「顔」を見せていただきました。なかには、疎遠になっていた家族を探し出すお手伝いをしたこともあります。
本当にいろんな人に出会いましたね。靴下の中に、わずかばかりのお金を隠してキューバからゴムボートで海を渡ってきた難民、二の腕に数字が刻まれてるホロコーストのサバイバー、第二次大戦からイラク戦争までを体験している退役軍人、内戦を逃れた移民……まさしく「人種のるつぼ」といわれるニューヨークです。いろんな人がいましたが、共通しているのは「それぞれにその人なりの幕引きの機会がある」ということ。さらに、その幕引きを意識することが、どれだけ大切かということも実感しました。
静かに旅立つ場に立ち会う機会が得られたとき、それまで抱いていた「死への漠とした恐怖感」は変化します。亡くなっていく人の死に対する姿勢や、命を生き抜いて旅立っていく姿は、残される人たちへの大きなギフトになるんです。
2年目の実習先は、「キャンサーケア」という患者支援団体でした。カルヴァリーでは終末期の患者さんだけでしたが、キャンサーケアでは、より幅広い病期の患者さんやご家族、ご遺族が対象で、個別カウンセリングやサポートグループを行っています。患者どうし、家族どうしなど、支え合いの力も見せてもらいました。仲間どうしの支え合いから有機的に生まれてくるサポートグループの場合、セラピストは細かな目配りをしながら、さまざまな語りの交通整理を行い「安全な場」を提供します。
非常にケアが充実している病院なので、どの患者さんも入院初日に、顔つきが和らぐんです。前にいた病院ではこんなに大変だったとか、闘病のしんどさを話して下さることもあれば、人生を振り返えられたり、それぞれの思いを大切な人たちに伝えたり……。カウンセリングを通じて、患者さんのさまざまな「顔」を見せていただきました。なかには、疎遠になっていた家族を探し出すお手伝いをしたこともあります。
本当にいろんな人に出会いましたね。靴下の中に、わずかばかりのお金を隠してキューバからゴムボートで海を渡ってきた難民、二の腕に数字が刻まれてるホロコーストのサバイバー、第二次大戦からイラク戦争までを体験している退役軍人、内戦を逃れた移民……まさしく「人種のるつぼ」といわれるニューヨークです。いろんな人がいましたが、共通しているのは「それぞれにその人なりの幕引きの機会がある」ということ。さらに、その幕引きを意識することが、どれだけ大切かということも実感しました。
静かに旅立つ場に立ち会う機会が得られたとき、それまで抱いていた「死への漠とした恐怖感」は変化します。亡くなっていく人の死に対する姿勢や、命を生き抜いて旅立っていく姿は、残される人たちへの大きなギフトになるんです。
2年目の実習先は、「キャンサーケア」という患者支援団体でした。カルヴァリーでは終末期の患者さんだけでしたが、キャンサーケアでは、より幅広い病期の患者さんやご家族、ご遺族が対象で、個別カウンセリングやサポートグループを行っています。患者どうし、家族どうしなど、支え合いの力も見せてもらいました。仲間どうしの支え合いから有機的に生まれてくるサポートグループの場合、セラピストは細かな目配りをしながら、さまざまな語りの交通整理を行い「安全な場」を提供します。
言葉だけに頼らないコミュニケーションが重要
大学院を無事修了しまして、1994年7月から、マウントサイナイ・メディカルセンターに勤務しました。大学病院ですので、教育的側面を重視し、さまざまな症例を受け入れる「ティーチングフロア」というのがありました。がんの患者さんだけでなく、エイズや糖尿病、保険に入っていない移民や生き倒れの方も入院してきます。
私の担当は内科のティーチングフロアと、中途で問題が生じて入院となる透析患者さんたち。急性期疾患に対応する病院なので、入院日数も短いのですが、危機的状況にある患者さんの問題点を把握し、不安や心の揺れに寄り添いつつ、その人の内的資源や物理的資源を見付け出し、安全に退院できるよう援助する役割は、カルヴァリーにはないスピード感でした。透析や腎移植などの患者さんやその家族に対し、精神面でのケアを研究する「サイコネフロロジー」という分野も、初めて知りました。
95年2月に、カルヴァリー・ホスピタルでポストが空いたと聞いて、文字どおりふたつ返事で転職を決めました。カルヴァリーは、最初に多くを学んだ場所ですから、私にとってはやはり原点です。
アメリカの医療現場で、外国人である自分がなぜ働くことができたかを考えてみると、カルヴァリーで培った経験が認められたことが大きかったと思います。それを支えたのは、「言葉だけに頼らないコミュニケーション」の重要性ですね。10年以上、アメリカで生活しているとはいえ、やはりネイティブと同レベルの語学力はありません。にもかかわらず対応している患者さんが本当に大切なことを教えてくれたのは、ネイティブでないからこそ、言葉をそのまま言葉として受け取らない、つまり言葉に込められた音やエネルギー、言葉を放つときの身振りや手ぶり、言葉と言葉の間に潜んでいる思いに敏感になるからだと思うんです。
病気を抱えていると、身体のエネルギーがだんだんと失われて行きます。それに伴って考える速度もゆっくりになっていきますし、患者さんが本当に大切なことを話そうとしているときや、気持ちや思いを的確に表現できる言葉を探そうとしているとき、「待つ」ということが重要なんです。母国語だと、ちょっとした沈黙も言葉で埋めたくなる衝動にかられるように思うのですが、さまざまなサインを受け止めながらのやんわりとした沈黙の中を待つことができたことで、患者さんが語れる、ちょうどいい「間」が生まれるのだと思います。
緩和ケアに限らず、ケアに携わる際に大切なのは、患者さんに対する関心だと思います。それとあわせて重要なのが、ちょっと離れたところから全体を俯瞰できることですね。私が尊敬する先生は、「観の目」という表現をなさっていますが、全体を俯瞰して、今起こっていることが全体の流れの中でどんな意味合いをもつかを感じる能力――「観の目」をどれだけ磨くかが、心理療法士をはじめ臨床家に求められる力だと思います。
私の担当は内科のティーチングフロアと、中途で問題が生じて入院となる透析患者さんたち。急性期疾患に対応する病院なので、入院日数も短いのですが、危機的状況にある患者さんの問題点を把握し、不安や心の揺れに寄り添いつつ、その人の内的資源や物理的資源を見付け出し、安全に退院できるよう援助する役割は、カルヴァリーにはないスピード感でした。透析や腎移植などの患者さんやその家族に対し、精神面でのケアを研究する「サイコネフロロジー」という分野も、初めて知りました。
95年2月に、カルヴァリー・ホスピタルでポストが空いたと聞いて、文字どおりふたつ返事で転職を決めました。カルヴァリーは、最初に多くを学んだ場所ですから、私にとってはやはり原点です。
アメリカの医療現場で、外国人である自分がなぜ働くことができたかを考えてみると、カルヴァリーで培った経験が認められたことが大きかったと思います。それを支えたのは、「言葉だけに頼らないコミュニケーション」の重要性ですね。10年以上、アメリカで生活しているとはいえ、やはりネイティブと同レベルの語学力はありません。にもかかわらず対応している患者さんが本当に大切なことを教えてくれたのは、ネイティブでないからこそ、言葉をそのまま言葉として受け取らない、つまり言葉に込められた音やエネルギー、言葉を放つときの身振りや手ぶり、言葉と言葉の間に潜んでいる思いに敏感になるからだと思うんです。
病気を抱えていると、身体のエネルギーがだんだんと失われて行きます。それに伴って考える速度もゆっくりになっていきますし、患者さんが本当に大切なことを話そうとしているときや、気持ちや思いを的確に表現できる言葉を探そうとしているとき、「待つ」ということが重要なんです。母国語だと、ちょっとした沈黙も言葉で埋めたくなる衝動にかられるように思うのですが、さまざまなサインを受け止めながらのやんわりとした沈黙の中を待つことができたことで、患者さんが語れる、ちょうどいい「間」が生まれるのだと思います。
緩和ケアに限らず、ケアに携わる際に大切なのは、患者さんに対する関心だと思います。それとあわせて重要なのが、ちょっと離れたところから全体を俯瞰できることですね。私が尊敬する先生は、「観の目」という表現をなさっていますが、全体を俯瞰して、今起こっていることが全体の流れの中でどんな意味合いをもつかを感じる能力――「観の目」をどれだけ磨くかが、心理療法士をはじめ臨床家に求められる力だと思います。
「心のエネルギー」を増やすノウハウを研究中
それぞれの人が本来もっている「癒す力」を賦活(ふかつ)させるための方法は、アメリカにいる間も含め、いろいろ学んできました。マッサージやリフレクソロジー、レイキ、アロマなど、心地良さを増やし、その人自身の「癒しの力」を賦活させる手段は、世の中にいろいろあります。それらをどう医療の現場に取り入れていくかは、今も研究中ですね。
しかし、少なくとも明らかなのは、心地良いと感じることで、人間は「心のエネルギー」を増やすことができるということです。「心のエネルギー」が増えると、病気になった自分と向き合えると同時に、自分自身に関わるスタミナが出てきます。
例えば、今までずっと言いたいことが言えずに、我慢に我慢を重ねた末に病気になってしまったとしましょう。病気のほうが治ったとしても、「言えない自分」を続けて行くと、身体は再び「もう一度、考え直そうよ」というサインを出してくる可能性もあるでしょう。
大切なのは、自分のなかで、自分が生きにくいと感じる部分、これまでの癖みたいなものを少し見直してみるということです。もちろん、自分のつらさや「生きにくくさせている癖」を見つめる作業には「心のエネルギー」が必要です。その「心のエネルギー」を充電するには、心地良さを自分のなかに見出したり、心地良さを体感すること。そうして、自分が養生することを、自分に許してあげられるようになると、心と身体、両方の健康に責任をもてるようになってきます。自分に優しくしてあげることで、最終的には誰もが本来もっている「全体性」を取り戻すことができるわけです。
「心のエネルギー」を増やし「全体性」を取り戻すには、いろいろな方法があると思います。カウンセリングだけではなく、ボディワークやアロマセラピー、アートセラピー、音楽療法など、いろんなアプローチが統合されて、医療の現場で活用されるといいなと思います。病院でのしくみとする前に、まずは自分の中でそういう手法を統合したいと思っているところです。
しかし、少なくとも明らかなのは、心地良いと感じることで、人間は「心のエネルギー」を増やすことができるということです。「心のエネルギー」が増えると、病気になった自分と向き合えると同時に、自分自身に関わるスタミナが出てきます。
例えば、今までずっと言いたいことが言えずに、我慢に我慢を重ねた末に病気になってしまったとしましょう。病気のほうが治ったとしても、「言えない自分」を続けて行くと、身体は再び「もう一度、考え直そうよ」というサインを出してくる可能性もあるでしょう。
大切なのは、自分のなかで、自分が生きにくいと感じる部分、これまでの癖みたいなものを少し見直してみるということです。もちろん、自分のつらさや「生きにくくさせている癖」を見つめる作業には「心のエネルギー」が必要です。その「心のエネルギー」を充電するには、心地良さを自分のなかに見出したり、心地良さを体感すること。そうして、自分が養生することを、自分に許してあげられるようになると、心と身体、両方の健康に責任をもてるようになってきます。自分に優しくしてあげることで、最終的には誰もが本来もっている「全体性」を取り戻すことができるわけです。
「心のエネルギー」を増やし「全体性」を取り戻すには、いろいろな方法があると思います。カウンセリングだけではなく、ボディワークやアロマセラピー、アートセラピー、音楽療法など、いろんなアプローチが統合されて、医療の現場で活用されるといいなと思います。病院でのしくみとする前に、まずは自分の中でそういう手法を統合したいと思っているところです。
「お見事」な最期に教えられた死の静けさ
患者さんと触れ合うなかで、自分自身の死生観も変わりましたね。この仕事をしていると、人生は最期そうそう悪いようにはしないものだということや、何かの出来事に「良い悪い」の意味付けをするのは自分だということ、そして必要なことは必要なときにちゃんと起きるということ、こちら側と向こう側はそんなに遠くないということを、患者さんから教えていただきます。
私が今、こういう仕事をしていることは、亡くなった両親も知っているように思いますね。もちろん肉眼では見ていませんけれど、緩和ケアの分野に方向転換をしてから、いろんなことがそういう方向に動き出して、私はただその流れに乗っているという感覚があります。もちろん、自分にそういう意思があるから、周囲の流れが変わったという言い方もできるのでしょうが。
多くの人に「死の恐怖」を超えるタイミングがあるような気がします。初めは「漠とした死」「限られた命」「死んで自分の存在がなくなること」「死の苦しみ」など、さまざまな恐怖があり、そこに向き合ったり、避けたりを繰り返しながら、気持ちの折り合いを見付けようとします。
だんだん身体がつらくなってくると「死が迫ってくる感じ」に実感が伴ってきて、体調がいいときは「まだまだ行ける」と感じ、不調なときは「もうだめかも」と感じる。あるいは、「死んだほうが楽になるのかもしれない」という思いがよぎることもあります。
身体の変化を体感する一方で、死の恐怖と対峙していくなかで、「自分なりの幕引き」を現実のものとして考えるようになります。前述の「静かな死」に立ち会った経験や、つらい症状を和らげることができる実感など、さまざまな体験を通じて、何らかの大きな力が働くためなのか、意識が拡大するためなのか、「命に連続性があること」を感じるようになる方は少なからずいます。
私たちが目指すのは、この「生と死の連続性のなかにいる」という感覚や、心のなかの静かな安定した場所――「安寧」と言われる部分に、患者さんたちがつながることです。本当に「お見事」という最期を遂げられた方々に教えられたのは、死の静けさですね。最終的にはすべてを委ねるという、その委ね方の塩梅が「お見事」につながるんだろうと思います。
「すごくシンプルで簡単なことなんだけどな」と、ある日、私にぽつんとおっしゃった患者さんがいました。「過去も未来も全部つながっている。先生も私も皆つながってる。ただそれだけのことなんだよね」と――。仕事のやりがいを感じるのは、そういう患者さんたちの変容を見るときです。最終的な「静かな場所」というのは、それぞれ自分自身で辿り着く以外に道はありません。私たちはあくまでそのお手伝いです。
患者さんたちが安寧を見いだすお手伝いができたと感じられるとき、ご自分の命を生ききった方の静かな最期に立ち会うことができたとき、この仕事をしていて良かったなと、心から思います。
私が今、こういう仕事をしていることは、亡くなった両親も知っているように思いますね。もちろん肉眼では見ていませんけれど、緩和ケアの分野に方向転換をしてから、いろんなことがそういう方向に動き出して、私はただその流れに乗っているという感覚があります。もちろん、自分にそういう意思があるから、周囲の流れが変わったという言い方もできるのでしょうが。
多くの人に「死の恐怖」を超えるタイミングがあるような気がします。初めは「漠とした死」「限られた命」「死んで自分の存在がなくなること」「死の苦しみ」など、さまざまな恐怖があり、そこに向き合ったり、避けたりを繰り返しながら、気持ちの折り合いを見付けようとします。
だんだん身体がつらくなってくると「死が迫ってくる感じ」に実感が伴ってきて、体調がいいときは「まだまだ行ける」と感じ、不調なときは「もうだめかも」と感じる。あるいは、「死んだほうが楽になるのかもしれない」という思いがよぎることもあります。
身体の変化を体感する一方で、死の恐怖と対峙していくなかで、「自分なりの幕引き」を現実のものとして考えるようになります。前述の「静かな死」に立ち会った経験や、つらい症状を和らげることができる実感など、さまざまな体験を通じて、何らかの大きな力が働くためなのか、意識が拡大するためなのか、「命に連続性があること」を感じるようになる方は少なからずいます。
私たちが目指すのは、この「生と死の連続性のなかにいる」という感覚や、心のなかの静かな安定した場所――「安寧」と言われる部分に、患者さんたちがつながることです。本当に「お見事」という最期を遂げられた方々に教えられたのは、死の静けさですね。最終的にはすべてを委ねるという、その委ね方の塩梅が「お見事」につながるんだろうと思います。
「すごくシンプルで簡単なことなんだけどな」と、ある日、私にぽつんとおっしゃった患者さんがいました。「過去も未来も全部つながっている。先生も私も皆つながってる。ただそれだけのことなんだよね」と――。仕事のやりがいを感じるのは、そういう患者さんたちの変容を見るときです。最終的な「静かな場所」というのは、それぞれ自分自身で辿り着く以外に道はありません。私たちはあくまでそのお手伝いです。
患者さんたちが安寧を見いだすお手伝いができたと感じられるとき、ご自分の命を生ききった方の静かな最期に立ち会うことができたとき、この仕事をしていて良かったなと、心から思います。
取材日:2011.2